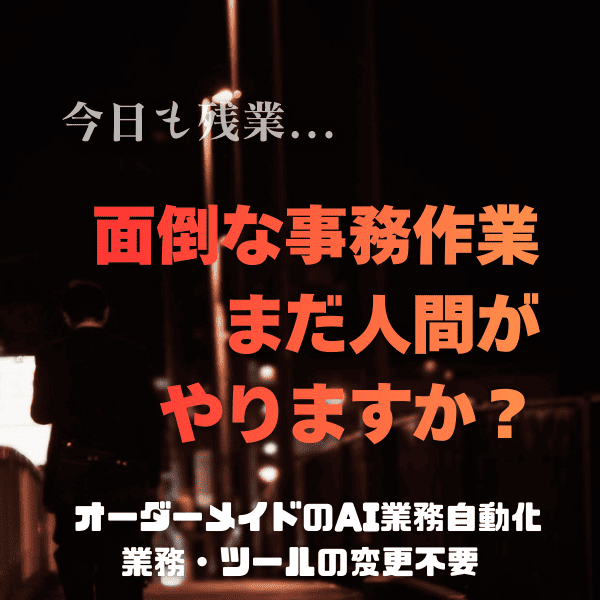ChatGPTの社内ルールを作らないと起こる4つのリスク
- 情報漏洩のリスク<顧客情報、個人情報>
- 業法違反のリスク<免許事業、資格事業>
- 著作権に関するリスク<生成テキスト、画像>
- 利用規約違反のリスク<ChatGPTの利用規約違反>
ご存じのようにChatGPTはチャット形式でお願いや質問をすると、膨大な情報から適していると思われる回答を生成してくれるAIです。ちょっと頭を使わないといけない新規の顧客への提案資料や問い合わせに対する返答でも、聞いてみるととりあえず考えるヒントは返してくれたり、質問の仕方を工夫すれば、適切な回答を返してくれたりもします。
しかしなんでも聞ける分、間違うと機密情報をChatGPT上に入力してしまったり、個人情報や著作権についても不明瞭なまま使ってしまう恐れがあります。
ただしご安心ください。きちんとリスクさえ把握しておけばこんなに便利なことはありません。
例えば、教育業界最大手のBENESSEなどは自社専用のChatGPTツールを作り、今まで8週間かかっていた業務を3週間で終わらせることが出来るようになったなどの報告もあります。このようにうまく使いこなせばこれまで以上の仕事を出来る、させてあげることが出来るようになるのがChatGPTのような新たな技術ですよね
そこで、この記事ではChatGPTを利用する場合にどんなリスクがあるのかを説明したうえで、それを回避するためにはどういった方法で社内ルールを作ればいいかをお伝えします。
ChatGPTの社内ルールを作らないと起こりうるリスク
なぜChatGPTの社内ルールを作らないといけないかというと、法律等に抵触する危険があるからです。ここで危険という言い方をしているのは、ChatGPTなどの生成AIは新しい技術であり、法律などで明確になっていない部分もあるからです。そこで本章では、どういったリスクがあるかについて理解していただき、自社としての対応を決めるためのサポートとしてお使いいただければと存じます。
情報漏洩のリスク<顧客情報、個人情報>

1つ目は『情報漏洩のリスク』です。
これはお客様の会社の機密情報や個人情報などが漏れてしまうことです。
具体的には、ChatGPTを使ってデータ分析をする際にお客様のお名前や年齢、性別などが含まれたExcelデータを渡してしまうことや提案資料を作るときにお願いしたいことと一緒に取引先企業名を入力して、その会社に対する提案を生成させてしまうなどがあるでしょう。
これらで対象になるのは、個人情報保護法や契約違反です。
個人を特定できるような情報が第三者の手に渡ってしまうことは個人情報保護の観点からNGですし、取引がある企業との秘密保持契約を締結している場合は、業務内で知り得た情報を第三者に漏らすのはNGです。
ChatGPTの場合、設定なしにこうした情報を入力してしまうと、学習データとして活用され、他の人のチャットで入力した機密情報などが出てしまう場合があります。ChatGPTの利用にはこうした情報漏洩のリスクが指摘されています。
業法違反のリスク<免許事業、資格事業>

2つ目は業法違反のリスクです。
これは許認可制の事業や資格型の事業などが該当します。
弁護士や社労士のような士業や医者などの専門性が必要で、資格や免許が必要な業務をChatGPTで代替することは違反となるリスクがあります。
ただしこれは士業や医師がChatGPTを使ってはいけないというわけではありません。
弁護士や社労士などが、顧客へのアドバイスをする際に自身で確認することなくChatGPTの内容をそのまま伝えていたら違反というだけであり、参考として使う分には問題ないといわれています。
あくまで資格や免許を持っている本人としてアドバイスを行うことが求められているということです。
ただし、その場合に個人が特定できるような情報(個人情報)を入力しないように注意する必要があります。
著作権に関するリスク<生成テキスト、画像>

3つ目は著作権に関するリスクです。
ChatGPTは世の中のデータを学習して生成しています。その参考元が非常に少ない場合、ほぼ元の情報がそのまま出てしまう場合があります。
ニッチな業界の情報や、画像などが時々ニュースになっていますね。
こちらは公開する前に必ず確認することで防ぐことができます。
そう考えると一般的な作業と同じですね。
利用規約違反のリスク<ChatGPTの利用規約違反>
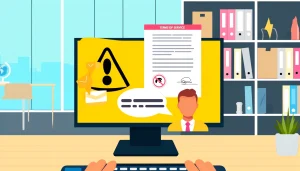
4つ目はChatGPTの利用規約違反のリスクです。
頻繁に更新されているので詳細はこちらをご確認下さい。
特に違反リスクがあるのは、SNS等への投稿についてです。
<該当箇所> ※2024年5月25日現在
OpenAI 利用規約より
- データ又はアウトプット(以下に定義します)を自動又はプログラムにより引き出すこと。
- 人が作り出したものではない場合に、アウトプットを人が作り出したものと表示すること。
ChatGPTで生成したコンテンツ(人の手を加えていないもの)については、人間が作成したと表示してはいけません。また、Botのように定期的にプログラムにより生成を指示し、自動で投稿するといったことも禁止されています。
ただ表記ルールについては、今後も変更されていくことが予想されるため、確認しながら柔軟に対応していきましょう。
ChatGPTを法人利用する上での情報セキュリティ対策はあるのか

次にこうしたリスクを踏まえてどのように情報セキュリティ対策をしていけばいいかをお伝えします。
学習データとして使わないよう設定する事は可能
まず前提として、ChatGPTのSettingから学習データとしては使わないという設定は可能です。
PC版のChatGPTなら右上のご自身のアイコンからSettings>Personalization>MemoryをOFFにすることで防ぐことができます。
これにより入力した機密情報や個人情報を学習して他の人のチャットの中で生成することは防げます。
その一方でまだ新しい技術ということもあり、今はどの企業も会社での利用について試行錯誤している状況です。
事業者向けプラン『ChatGPT Enterprise』であればセキュリティ対策は◎
ただしこれらの話やChatGPTの情報漏洩に関する話はあくまで個人利用プランに関する話です(ChatGPT4、ChatGPT4o:2024年5月24日現在)。
ChatGPTの事業者向けプラン『ChatGPT Enterprise』であれば、法人利用に耐えうるセキュリティ対策がなされていると言えます。
具体的には、顧客情報を扱うサービスの米国の情報セキュリティ監査基準SOC2に準拠し、データの送受信はMicrosoftも推奨しているプロトコルTLS1.2を、保存データは、政府機関や金融機関など、高度なセキュリティが必要とされる分野でも数多く使用されるAES 256を用いて暗号化されています。
小規模事業者向けにChatGPT Teamも登場
ChatGPT Enterpriseはセキュリティなどの面では非常に安心ですが、大規模事業者をメイン顧客として設定しており、プランも個別見積です(個人向けの有料プラン20ドル/月と比べるとかなり高額であるといわれています)。
しかし個人に全て任せるのは不安・・・という人には小規模事業者から使えるChatGPT Teamというプランが登場しました(1人当たり月30ドル(年間払いなら25ドル/人・月)。
こちらは、最初から利用したデータや会話履歴が学習に利用されなくなっています。
ひとりひとり学習データとして利用しない設定をしないと漏洩のリスクがあるとなると法人としての導入は怖い部分がありますよね?そうした場合に有効です。
また、ChatGPT Teamでは、チームで使うための招待や権限設定が可能であり、誰を参加させるかなどの管理が可能です。これによりアカウントの一元管理が可能となります。
誰かが退社したのにずっとアカウントが付与され続けてしまっていたとか、権限の設定をマネジメント側で制御できていない状況を回避できます。
最後にOpenAIへのハッキングについてですが、SOC2に準拠しているということですが、まだ具体的なプロトコル等の情報は出てきませんでした。
ワークスペースとして切り出されているので個人向けよりは安全だとは思いますが、もし漏洩してしまった場合に自社の責任になる部分もゼロではないので、研修などでリスクを理解してもらったり、入出力の社内ルールを決めて対応する必要があるでしょう。
まとめるとChatGPT TeamはEnterprise版では予算感が読めない、まだどれくらい使うか微妙という方はChatGPT Teamを検討してもよいでしょう。
OpenAI(ChatGPTの運営元)に情報が渡るのはいいのかについて
最後に、ChatGPT Enterpriseで第三者に情報が漏れるのは防げることは分かったが、OpenAI(ChatGPTの運営元)にそうした機密情報などが渡るのは大丈夫なのかについても念のため説明いたします。
結論は問題ありません。例えば、あなたはGmailなどのメールサービスを使って重要な機密情報のやり取りをしていませんか?それと同様のことがChatGPTにも言えます。
プライバシーポリシーで個人情報の利用範囲を定義していたり、前述のSOC2やTLS1.2+などでセキュリティ対策を行っていたりするEnterprise版であれば、問題なくお使いいただけるでしょう。
・まとめ
- ChatGPT Enterpriseであればセキュリティは問題なさそう(ただし費用は要見積)
- ChatGPT Teamは小規模事業者(推奨2名~150名)までならコスパよさそう
- 個人向けプランは「学習データとして活用しない」設定をすることで第三者のチャットで出力される事は防げる
- セキュリティの面では無料<有料<ChatGPT Teams<ChatGPT Enterpriseとなる
ChatGPTの社内ルールを作るときのポイント

ChatGPTの社内ルールがないことのリスクを踏まえて、本章では社内ルールを作るときのポイントをお伝えしていきます。社内ルールと言っても何を決めればルールが出来たことになるのか不明瞭ですよね。ここではシンプルに入力と出力に対してルールを決めることと、使う人を決めることについてお伝えしていきます。
入力に対してのルールを設ける<利用用途、プロンプトなど>
一つ目は利用用途や使用するプロンプトを決めて使うといったことです。
利用用途
業務別に利用の可否を定義しておけば、業法違反のリスクは避けれられるでしょうし、個人情報漏洩のリスクについてもある程度は防ぐことができるでしょう。
また、この際「なぜこの業務では使ってよいのか」「なぜこの業務では使ってはいけないのか」を説明してあげるとより効果的な抑止になります。
プロンプト
プロンプト(ChatGPTに入力する文章のこと)を決めてしまう方法もあります。
こちらは前提、利用用途が絞られている必要がありますが、特定の業務に対して最適なプロンプトを用意しておいて、その中で状況に合わせて変える部分を先に定義しておくといった方法があります。
例えば、SEO対策をした記事を書く業務にChatGPTを使う場合、以下のことを必ず入れるようにプロンプトを組んでおく等が考えられます。
- どんな記事か
- ターゲット
- 悩み
- 理想の状態
- 出力条件
これらに対して具体的な参考プロンプトを入れておき、必要に応じて変更してもらうようにすると、生成内容の質も上がりますし、社員のChatGPT利用の教育にもなります。
出力されたものの利用に対してルールを設ける<そのままの利用禁止など>
2つ目はChatGPTが生成した画像やテキストの利用ルールです。
わかりやすい例でいうと、「生成されたものは確認なしで利用してはいけない」「生成した画像は必ず画像検索で同じものがないかを確認する」などがあります。
また、事業を左右する大きなものなど、重要度が高いものについては、承認フローを設けるなどのやり方もあります。
利用者を制限する方法もある
今までは利用方法についての話でしたが、3つ目は利用者についての話です。
そもそも使っていい職種や職位を限定してしまうやり方もあります。
例えば、機密情報に接する可能性が高い業務を行っている人は利用を制限し、逆に公開情報(SNSやサイトへの投稿など)を行う仕事については問題ないとしてしまう方法もあります。
業務フローに組み込むやり方もある<議事録など>
4つ目はタイミングの話です。業務フローの中のこのタイミングで利用するのように決めてしまう方法があります。
例えば、ある会社では、音声の文字おこしサービスを使って会話を文字おこしして、それをChatGPTに議事録として整理させることで議事録作成業務を大幅に短縮した事例があります。 ※この場合、内部情報を扱うので必ずMemoryはOFFにしてください。
このように業務のどこで使うかを定義することで効率化につなげる例もございます。
ただし詳細に決めすぎるのではなく個別稟議で固めていく方がいい
これまで4つの社内ルールの決め方についてお話してきましたが、最後にあまりがちがちにやり過ぎない方がいいというお話をさせてください。
繰り返しになりますが、ChatGPT自体がまだまだ新しく、機能的にも、法規制的にも変化し続けています。
そしてChatGPTを業務で利用することについても、まだ各社試行錯誤しながら進めている状態です。
この状況であまりルールでがちがちに縛ってしまうと使われなくなってしまったり、本来のChatGPTの性能を活かしきることができなくなってしまいます。
どちらかといえば、最低限のリスクを理解してもらいながら、あとは「こんな風に使うと業務のクオリティやスピードがこれくらい変わるよ!」と提案的にいろいろ伝えてあげる。
わからない部分は個別の稟議や担当者へ確認してもらいながら一緒に作っていく。というのが今まで見てきた中でうまくいっている企業の事例でした。
ChatGPTの社内ルールの事例<WEB制作会社の例>

それではここからChatGPTの社内ルールの事例をご紹介します。今回はWEB制作会社でChatGPTを業務で利用する場合の社内ルールの事例です。
利用用途と基本方針の例
まずどのような用途に使うのか(利用用途)と業務に使う場合の基本方針を決めます。具体的な作業に対しての利用規定は後述しますが、まず大枠の方針を決定します。
利用用途に関する考え方:仕事上で作成する文書やアイディア出しに用いる
<利用用途の例7つ>
- WEBコンテンツの文書生成
- 広告、マーケティングコピーのアイディア生成
- 問い合わせの自動応答
- プロジェクト管理に必要なドキュメント作成
- コード生成とデバッグ
- UIUXデザインのアイディア生成
- 翻訳と多言語対応
基本的な利用方針:顧客に知られても問題ない範囲に限定する
<基本方針>
基本的にChatGPTの利用は、あくまでサポートやたたき台の位置づけとし、人のレビューや承認なしで公開したり、顧客へ送ってはいけないものとする。
承認や公開に当たっては以下のチェックリストを元に問題ないことを確認する
<公開・承認のチェックリスト例>
- ChatGPTに入力情報は公開情報もしくは特定の個人や組織が特定できない情報に限定する
- 生成されたアウトプットは必ず正しい情報であるか、他の誰かの作成したものではないか(著作権に触れていないか)を確認する
- ChatGPTを業務で利用する前に必ず研修、もしくはそれに類するビデオなどで学習し、利用ポリシーなどや著作権、個人情報、機密情報の扱いなどを理解した上で利用する
- その他、不明な部分については個別の相談や稟議申請で対応するものとする
上記のような基本方針を決めたうえで各業務の具体的な利用シナリオやルールについて決めていきましょう。
WEBコンテンツの文書生成の例
ここから具体的な利用用途に対するルールを記載します。具体的にどんな作業に対して使うことが想定されるのか(具体的なタスク)、その際にどんなものをChatGPTに生成してもらうのか(アウトプット)を想定したうえで、利用規定を考えていきます。
それではまず『WEBコンテンツの文書生成』に利用する場合のルールから考えていきます。
<利用規定>
- 具体的なタスク: ブログ記事、製品説明、FAQセクションの文章作成。
- アウトプット:文章の作成、文章構成の作成、SEOを考慮したキーワード出し
- 使用基準:原則として初稿の生成に使用。最終的なコンテンツは人間によるレビューと編集を必須する。
- SEO対策: 生成されたコンテンツは、SEOガイドラインに沿っていることを確認し、必要に応じてキーワードの調整を行います。
- 著作権遵守: コンテンツに第三者の著作物を使用する場合は、適切な許可を得るか、著作権に違反しない範囲で使用します。
- 利用方法:想定している記事のキーワードやターゲット、この記事でのゴール(CV)などを入力し、その他に考えられるキーワードや構成、文章を生成する
では次に実際のプロンプトの例をご紹介します。例として20代と30代のビジネスパーソンに対して、キャリアチェンジやスキル向上のためのマーケティングスクールの選び方を伝える記事を考えてもらいましょう。SEOを考慮したキーワード、タイトル、記事の構成を考えるプロンプトの例を以下に示します。
<プロンプト例>
あなたはSEOマーケティングのプロとして、以下の条件におけるキーワード案と記事の構成を考えてください。
#どんな記事か
マーケティングのスクールの選び方を伝える記事
#ターゲット
20代、30代のビジネスパーソンの中でもキャリアを変えたい、スキルを身に着けたいと思っている人
#悩み
このままでは将来のキャリアに明るい展望が見えない
#理想の状態
自分なりのスキルをもってやりたいことをできている状態
#出力条件
1. SEOを考慮したキーワード候補を10個
2. SEOを考慮したタイトル候補5個
3. SEOを考慮した記事の構成(H2とH3まで)
—————————-
上記のプロンプトを元に生成されたアウトプットをいかに示します。
<アウトプット例>
①SEOを考慮したキーワード候補(10個)
- マーケティングスクールの選び方
- キャリアチェンジ ビジネススキル
- 30代 ビジネススクール選び
- 20代 キャリアアップ 教育
- スキルアップ マーケティング教育
- ビジネスパーソン キャリア形成
- 将来のキャリア設計
- マーケティング研修選び
- 自己啓発 ビジネス教育
- 効果的なビジネススクール探し
SEOを考慮したタイトル候補(5個)
- “30代ビジネスパーソン向け: 効果的なマーケティングスクールの選び方”
- “キャリアアップの鍵: 20代・30代のためのビジネススクール選び”
- “将来のキャリアに差をつける: マーケティングスキル向上のステップ”
- “ビジネススキルを磨く: 適切なマーケティング教育の選び方”
- “自己啓発とキャリア形成: 効果的なビジネススクールの見つけ方”
SEOを考慮した記事の構成
- H2: マーケティングスクール選びの重要性
- H3: キャリアチェンジのための教育の役割
- H3: スキルアップと自己実現の道
- H2: 20代・30代ビジネスパーソンのための選択基準
- H3: キャリア目標に合わせたスクール選び
- H3: 教育内容とカリキュラムの比較
- H2: スクール選びで考えるべきポイント
- H3: 講師の質と実績
- H3: 卒業後のキャリアサポート
- H2: 成功事例と生徒の声
- H3: キャリアアップに成功した卒業生の声
- H3: スクール選びの成功ポイント
- H2: 最終的な選択をする前に
- H3: 資料請求とオープンキャンパス参加の重要性
- H3: じっくりと検討するためのチェックリスト
このように、ブログや製品説明、FAQ(よくある質問)等の文章を考える時の最初の方向性を考えるときや、構成を考える際に使うことができます。
特にChatGPTのような生成AIはSEOのようなある程度体系化されたノウハウに強い。
1つの文章を作成する際に抜けもれなく項目を考えたりするのは得意なので、そのような最初の悩む時間のサポートに使えます。
ただしその際には最終的に後悔する前に必ず人間がレビューするようにしてください。
特にSEOガイドラインは適宜アップデートされるので、場合によってはキーワード等の修正が必要だったり、生成された文章が正しい情報であることの確認も怠ってはいけません。
広告、マーケティングコピーのアイディア生成の例
2つ目は『広告、マーケティングコピーのアイディア生成』です。
広告やLP、記事などのキャッチコピーなどを使う場合のChatGPT利用例です。
まずは以下のように利用方針を作成します。
利用方針
- タスク: 広告文やマーケティングコピーの生成
- アウトプット: 広告文の生成やコピーのアイディア出し
- オリジナリティ: コピーがオリジナルであることを必ず確認する
- ブランドガイドライン: すべての広告文は、企業のブランドガイドラインと一致するように管理する
- 利用方法:想定しているターゲット、そのターゲットが持っている悩み、彼らが求めている理想の状態(ベネフィット)、商品のメリットなどを入力して、広告文やコピーを生成する
<プロンプト例>
これから我々はタスク管理ツールのプロモーションを行います。あなたは以下の条件を元にコピーライターとして、広告のコピーを考えてください。
#商材
タスク管理ツール
#ターゲット
新たな取り組みを始めたいと思っているがなかなか前に進まないと感じている中小企業の経営者
自分以外にマネジメント出来る人がいなくて中間層のマネジメント力強化が急務だと感じている中小企業の経営者
#商材の特徴
ITに不慣れな人でも簡単に使えるユーザビリティに配慮した設計
スマホのみで操作が完結できるのでPCが苦手な人でも安心して使える
#悩みと解決策
ゴール(目標)に対する自分たちのしなければいけないこと(タスク)が可視化されるので、目標達成のために何をやらなければならないかといった大局的な視点が身につく
#出力条件
上記の条件を元に広告コピーを10個出してください
その10個のコピーはリスティング広告でも使えるようなものとしてください
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下は、指定された条件に基づいて考案したタスク管理ツールのプロモーション用コピーです。これらはリスティング広告にも適しています。
「進まぬ業務、解決へ導く。手軽さにこだわったタスク管理ツールで、中小企業の明日を変える。」
「目標達成、もう迷わない。全てのタスクを可視化、中小企業の経営者に革命を。」
「スマホ一つで、経営の効率化。IT初心者も安心のタスク管理ツール。」
「マネジメントの悩み、ここに解決策。中間層を強化する、簡単操作のタスク管理ツール。」
「新たな取り組み、スムーズに。簡単操作で目標をクリアするタスク管理ツール。」
「PC不要、スマホで完結。中小企業経営者のためのタスク管理ツール。」
「目標達成への道筋が見える。中小企業向け、使いやすいタスク管理ツール。」
「マネジメント力、手軽にアップ。タスク可視化で、経営の質を高める。」
「経営の悩み、一つずつ解決。直感的操作で進む、タスク管理ツール。」
「次の一歩を踏み出すサポート。中小企業の成長を加速するタスク管理ツール。」
これらのコピーは、中小企業の経営者が直面する課題やニーズに焦点を当て、タスク管理ツールの利便性と効果を強調しています。
こちらはキャッチコピーや広告文を考える時に使えるといっています。ChatGPTは「○○の案を10個出してください」のようにお願いすると、いくらでも案を出すことができるのでアイディア出しには非常に有効です。
ただし”他ですでに使われていないか”と”そのアイディアは企業のコンプライアンスや倫理的に問題ないか”については必ず人がレビューするようにしましょう。
問い合わせの自動応答
<利用規定>
- タスク: クライアントからの問い合わせへの自動応答
- アウトプット: 迅速で明確なコミュニケーション、顧客満足度の向上。
- 応答品質: 自動応答は、明確かつ正確で、専門的なトーンであることを保証します。
- 個人データ保護: クライアント情報の取り扱いには最大限の注意を払い、個人情報保護法に準拠します。
<プロンプト例>
あなたはカスタマーサポートで長年の経験を積んだ顧客ロイヤリティ向上のプロフェッショナルです。以下の問い合わせ内容に対しての回答を考えてください。
#問い合わせ内容
小学校3年生の子供がいる母です。子供に初めての学習教材の購入を考えています。どれから始めたらいいかアドバイスください。
#出力条件
1. 問い合わせをした人はどのような悩みを持っているか200文字以内で説明してください
2. その悩みに対してどのようなアドバイスをすべきか200文字以内で説明してください
3. 問い合わせに対する回答を考えてください
<生成例>
問い合わせの内容に関する悩みの説明
お問い合わせいただいた方は、小学3年生のお子様に最適な学習教材を初めて購入しようとしており、どの教材から始めれば良いかについて不安や迷いを感じています。教育に関する選択は子供の学習意欲や成長に大きな影響を与えるため、最適な選択をしたいという願いがあると思われます。
アドバイス
お子様の興味や学習レベルに合わせた教材を選ぶことが重要です。例えば、算数や国語の基礎を固めるための教科書に沿ったドリルや、子供の好奇心を刺激する科学実験キットなどがおすすめです。また、読書を促進するために、年齢に合った児童書を選ぶのも良いでしょう。
回答
ご質問ありがとうございます。お子様の学習教材選びについてのご相談、承りました。小学3年生であれば、まずは基本的な算数や国語の理解を深めるための教科書に沿ったドリルから始めるのが良いでしょう。また、お子様が特に興味を持っている分野があれば、それに関連する学習教材を選ぶのも効果的です。例えば、科学や自然に興味があれば、実験キットや自然観察用の教材が喜ばれるかもしれません。読書を促すために、お子様が楽しめる児童書を一緒に選ぶのも良い方法です。教材選びはお子様の興味や学習レベルに合わせて行うことで、学習意欲を高めることができます。お子様に合った学習のスタートを応援しています!
ーーーーー
顧客からの問い合わせに対しての回答のアドバイスをもらう時の使い方です。ポイントとしては、単に回答例だけを生成してもいいのですが、その前に悩みやアドバイスの方針も聞いておくと考えるサポートになるということです。
また、入力をする際にはお客様のお名前や個人を特定できるような情報が含まれている場合には一般化するなど、修正が必要です。
また今回はChatGPTの基本機能のみでの事例をご紹介しましたが、自社の製品データを用いて、具体的な商品の説明を出来るようにする”ChatGPT Builder(GPTs)を用いたやり方”もあります。
プロジェクト管理に必要なドキュメント作成
<利用規定>
- タスク: ミーティングのメモ、プロジェクトのドキュメント、進捗報告書の作成。
- アウトプット:プロジェクト管理に必要な様々なドキュメントが適切で整理されたフォーマットで生成される。
- 情報の正確性: 生成されたドキュメントは、事実確認と校正を経て、誤りがないことを確認します。
- 文書管理: すべてのドキュメントは、適切なアクセス制御と保存プロセスを通じて管理されます。
<プロンプト例|議事録の項目>
以下に打ち合わせ時のメモがあります。その情報を元に、指定した項目にあてはまるように議事録として整理してくれますか?
#打ち合わせメモ
2024年1月10日 10:00-11:30(会議室B)
参加者:田中さん(プロマネ)、鈴木さん(デザイナー)、佐藤さん(開発者)、山田(マーケ) ※伊藤さん(開発者)は体調不良で欠席
会議の目的:
新プロジェクト「X」の初期計画とタスクの割り当て
議題:
プロジェクトの概要と目標
デザイン要件の確認
開発スケジュールの設定
マーケティング戦略の検討
PJTゴール:3か月以内にプロトタイプ完成を目標とする(田中)⇒全員合意
デザイン:デザイン案が承認され、次回までに詳細な仕様を作成(鈴木:1/20)
開発:開発フェーズの提案とリソースのリストアップ⇒スケジュール案を承認し伊藤の復帰後にタスク確認(1/17)
マーケ:初期の市場調査結果を共有、ターゲット顧客層の提案⇒マーケティングプランを詳細化して次回の会議で報告(山田担当:1/24)
次回会議:1/25 10:00、会議室B
その他:伊藤の体調に配慮し、サポートを検討
#議事録の項目
日付と時間:
会議の開始と終了の日時を記録します。
出席者と不在者のリスト:
出席者の名前を列挙し、不在者がいればその理由を簡潔に記述します。
会議の目的:
会議の主な目的や目標を明確に記述します。
議題:
議論される各トピックをリストアップし、それぞれについての簡単な説明を加えます。
討議内容と決定事項:
各議題についての主要な討議点、提案、意見、決定事項を詳細に記録します。
誰がどのような意見を述べたか、具体的な決定があればそれを記述します。
アクションアイテム:
各決定に基づく具体的なアクションアイテムをリストアップします。
誰が何を担当するか、期限はいつかを明記します。
次回会議の日程:
次回の会議の日時や場所(もしあれば)を記載します。
その他の注記:
会議中に生じた特別な問題や注目すべき事項があれば、それを記録します。
以下は、提供された打ち合わせメモを基に整理した議事録です。
<生成例>
プロジェクト会議 議事録
日付と時間: 2024年1月10日 10:00 – 11:30
場所: 会議室B
出席者:
田中さん(プロジェクトマネージャー)
鈴木さん(デザイナー)
佐藤さん(開発者)
山田さん(マーケティング)
不在者:
伊藤さん(開発者)- 体調不良による欠席
会議の目的:
新プロジェクト「X」の初期計画とタスクの割り当て
議題:
プロジェクトの概要と目標
デザイン要件の確認
開発スケジュールの設定
マーケティング戦略の検討
討議内容と決定事項:
プロジェクトの概要と目標
田中さん提案: 3か月以内にプロトタイプ完成を目標とする。
決定: 全員が目標に合意。
デザイン要件の確認
鈴木さん: デザイン案が承認され、次回までに詳細な仕様を作成。
決定: 仕様書の作成期限を1月20日に設定。
開発スケジュールの設定
佐藤さん: 開発フェーズの提案とリソースのリストアップ。
決定: スケジュール案を承認し、伊藤さんの復帰後にタスク確認。
アクションアイテム: 開発スケジュールの確定(期限: 1月17日)
マーケティング戦略の検討
山田さん: 初期市場調査の結果共有とターゲット顧客層の提案。
決定: マーケティングプランを詳細化して次回の会議で報告。
アクションアイテム: マーケティングプランの詳細化(期限: 1月24日)
次回会議の日程:
2024年1月25日 10:00、会議室B
その他の注記:
伊藤さんの体調に配慮し、必要に応じてサポートを検討。
この議事録は、会議の重要な内容と決定事項を明確に記録し、アクションアイテムには担当者と期限が指定されています。これにより、プロジェクトの進捗を効率的に管理し、関係者が必要な情報を参照できるようになっています。
プロジェクト管理のための文書作成に対しての使い方です。一般に、プロジェクトを管理し、進めていくために、複数のドキュメント(文書)を使いながら進めていきます。その時の文書作成や項目だし、テンプレート作成等に活用できます。
このプロンプトは打ち合わせメモを議事録の項目に合うようにまとめてもらうためのものです。このように雑記スタイルでも議事録としてまとめてくれるので作業を削減することができます。
また、プロジェクト計画書やWBSなど、プロジェクト管理に必要なドキュメントに必要な項目を出すのもスムーズでしょう。
また、今回は社内の人の名前のみのためそのまま記載しましたが、顧客との打ち合わせをした場合には顧客の名前や、機密情報などが含まれる場合があるのでご注意ください。入力時に一般化するなどして使用するようにしましょう。
また社内のものであっても極秘プロジェクトの場合や自社のコンプライアンスに違反する場合などは固有名詞を使わないなど、さらに厳重に対応が必要な場合もあります。
また、こちらも人のレビューなしで回遊されないように注意しましょう。
コード生成とデバッグ
<利用規定>
- タスク: ウェブ開発における基本的なコードの生成、バグの特定と修正案の提案。
- アウトプット: 開発時間の短縮、デバッグプロセスの効率化。
- コードの検証: ChatGPTによって生成されたコードは、適切なテストとレビューを経て、品質とセキュリティを確保します。
- コードの使用基準: 自動生成されたコードは、基本的な機能のみに使用し、複雑な機能やセキュリティに関わる部分は専門家のレビューを受けます。
<プロンプト例>
HTMLとCSSを使用して、シンプルでモダンなレスポンシブメニューのコードスニペットを生成してください。メニューはモバイルビューでハンバーガーアイコンに変わり、デスクトップビューでは水平方向のナビゲーションバーとして表示されるようにしてください。以下の要件を満たしてください:
- HTML構造: <nav> タグを使用し、メニューアイテムは <ul> と <li> で構成されていること。
- CSSスタイリング: メニューはスタイリッシュで、現代的なデザインを持つこと。メディアクエリを使用して、モバイルとデスクトップビューのレイアウトを切り替えます。
- レスポンシブ動作: JavaScriptは使用せず、CSSのみでモバイルビュー時のハンバーガーアイコンの表示とメニューの展開を実現すること。
- アクセシビリティ: キーボードナビゲーションとスクリーンリーダーに対応すること。
メニューアイテムは「ホーム」「サービス」「プロジェクト」「コンタクト」の4つとします。
ーーー
<生成例>
以下は、指定された要件に基づいたレスポンシブメニューのHTMLとCSSコードです。
HTMLコード
<nav>
<label for=”toggle”>☰</label>
<input type=”checkbox” id=”toggle”/>
<ul id=”menu”>
<li><a href=”#home”>ホーム</a></li>
<li><a href=”#services”>サービス</a></li>
<li><a href=”#projects”>プロジェクト</a></li>
<li><a href=”#contact”>コンタクト</a></li>
</ul>
</nav>
CSSコード
/* 基本スタイル */
nav {
overflow: hidden;
background-color: #333;
}
nav label {
display: none;
font-size: 30px;
cursor: pointer;
}
nav ul {
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
nav ul li {
float: left;
}
nav ul li a {
display: block;
color: white;
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;
}
nav ul li a:hover {
background-color: #111;
}
/* レスポンシブスタイル */
@media screen and (max-width: 600px) {
nav ul {
display: none;
}
nav label {
display: block;
}
nav input[type=checkbox]:checked + #menu {
display: block;
}
nav ul li {
float: none;
display: block;
text-align: left;
}
}
このコードは、モバイルビューでハンバーガーアイコンを表示し、デスクトップビューで水平方向のナビゲーションバーとして表示されるレスポンシブメニューを作成します。CSSメディアクエリを使用して、画面サイズに応じて表示を切り替えます。
ーーー
このように特定の機能の基本的なコード生成などはChatGPTに依頼すると生成してくれます。今回はプロンプトからChatGPTに作ってもらいました。
このように多少の修正やボタンのデザイン変更であれば、エンジニアでなくても可能になります。
ただし、最終的に公開する前には必ずプロの目でチェックやテストを行うようにしましょう。
UI/UXデザインのアイデア生成:
<利用規定>
- タスク: ユーザーインターフェースデザインのアイデアやユーザーエクスペリエンスの改善提案。
- アウトプット: イノベーティブでユーザーフレンドリーなデザイン案。
- デザイン標準の遵守: 生成されたデザイン案は、ユーザビリティとアクセシビリティの標準に準拠していることを確認します。
- クリエイティブプロセスの支援: ChatGPTは、デザインのアイデア生成にのみ使用し、最終デザインは専門家によって決定されます。
<プロンプト例>
当社のウェブサイトは現在、ナビゲーションが複雑で、ユーザビリティに問題があるとのフィードバックを受けています。以下の情報に基づいて、ナビゲーションを改善するための具体的な提案をお願いします。
1.サイト構造:
メインセクションは「ホーム」、「製品一覧」、「サービス」、「お問い合わせ」です。
「製品一覧」には複数のサブカテゴリがあり、それぞれに多数の商品ページが連なっています。
2.ユーザーフロー:
ユーザーは主に「製品一覧」から商品を閲覧し、「商品詳細」ページで情報を得た後、購入に進みます。
情報検索のために「FAQ」や「サービス」セクションも頻繁に訪れます。
3.ユーザーフィードバックとデータ:
ユーザーからは、特に「製品一覧」のナビゲーションがわかりにくいとの声が多いです。
ページ訪問データからは、「製品一覧」から「商品詳細」への移行率が低いことがわかっています。
4.競合他社との比較:
競合他社のサイトは、シンプルなドロップダウンメニューとビジュアル要素を使用して、直感的なナビゲーションを提供しています。
5.ビジュアルエレメント:
当社サイトは青と白のカラーパレットを使用しており、クリーンでモダンなデザインを意識しています。
ボタンとフォームは角を丸くしたデザインで統一されています。
6.技術的仕様:
当社サイトはWordPressを使用しており、全体的にレスポンシブなデザインとなっています。
アクセシビリティの観点では、スクリーンリーダー対応やキーボードナビゲーションに配慮しています。
7.シナリオベースの質問:
もしユーザーが特定の製品カテゴリを素早く見つけたい場合、どのようにナビゲーションを改善できるでしょうか?
モバイルユーザーがサイトを訪れた際、どのようなナビゲーション体験を提供すべきでしょうか?
ーーー
<生成例>
あなたのウェブサイトのナビゲーションを改善するための提案は次のとおりです。
メガメニューの導入:
「製品一覧」セクションにメガメニューを導入します。これにより、ユーザーはメインメニューから直接サブカテゴリにアクセスできます。
サブカテゴリをビジュアルリッチな形式で表示し、ユーザーが求める製品を素早く見つけられるようにします。
ナビゲーションの視覚的改善:
青と白のカラーパレットを活用して、ナビゲーションバーのコントラストと視認性を高めます。
アイコンやサムネイル画像を使用して、各セクションとサブカテゴリを直感的に識別できるようにします。
インタラクティブなサイドバーの追加:
「製品一覧」ページに、折りたたみ可能なサイドバーを追加します。このサイドバーには製品カテゴリがリストされ、ユーザーが目的のセクションに迅速にナビゲートできるようにします。
検索機能の強化:
サイトのヘッダーに目立つ検索バーを配置し、ユーザーがキーワードで素早く製品や情報を検索できるようにします。
検索機能にオートコンプリートとフィルター機能を追加します。
モバイルファーストのアプローチ:
モバイルユーザーに対しては、タッチフレンドリーなメニューボタンとスワイプ可能なカテゴリスライダーを提供します。
画面サイズが小さいモバイルデバイスでもナビゲーションが容易になるよう、メニューアイテムの間隔を広げます。
ユーザーフィードバックの活用:
ユーザーフィードバックを基に、ナビゲーションのユーザビリティテストを実施し、さらなる改善点を特定します。
A/Bテストを通じて、異なるナビゲーションデザインの効果を評価します。
これらの改善提案を実施することで、ユーザーのサイト内ナビゲーション体験が向上し、製品へのアクセスや情報検索が容易になるとともに、全体的なユーザーエンゲージメントと満足度が高まることが期待されます。
翻訳と多言語対応:
<利用規定>
- タスク: ウェブサイトコンテンツの多言語翻訳。
- アウトプット: 幅広いオーディエンスにアピールする多言語コンテンツ。
- 翻訳品質: 生成された翻訳は、文脈と文化的なニュアンスを適切に反映するようにします。
- レビューと校正: 翻訳されたコンテンツは、ネイティブスピーカーによる校正を必須とします。
<プロンプト例>
当社のウェブサイト用に日本語で作成したコンテンツを、英語に翻訳してほしいと考えています。以下の日本語のテキストをこれらの言語に翻訳してください。
日本語のコンテンツ:
“当社のウェブサイトへようこそ!私たちはあなたのニーズに合った幅広い製品とサービスを提供しています。最新のテクノロジーガジェットを探している方も、専門的なサービスを求めている方も、当社にはすべてが揃っています。今すぐ製品カテゴリをブラウズして、当社の特別なオファーを発見してください。”
このテキストは、ウェブサイトのホームページに掲載され、さまざまな言語を話す訪問者に当社の製品とサービスを紹介するために使用されます。翻訳されたテキストは、それぞれの言語の話者に対して自然で理解しやすく、文化的な要素を考慮したものであることが望まれます。
<生成例>
以下は日本語のコンテンツを英語に翻訳したものです。
English Translation:
“Welcome to our website! We offer a wide range of products and services tailored to your needs. Whether you are looking for the latest tech gadgets or professional services, we have everything you need. Browse our product categories now to discover our special offers.”
翻訳や他言語対応に利用するうえでの注意点は”1回の生成では1つの言語しかできない”ということです。同時に英語、スペイン語、フランス語のように複数の言語に対応することはできません。
また、プロンプト例の後半部分にあるようにウェブサイトに公開されることや文化的な要素を考慮することを含めることでより適切なニュアンスも伝わりやすくなります。
そうは言ってももちろんChatGPTも翻訳を必ず完ぺきに行えるわけではないので、もし可能であればネイティブスピーカーなどのチェックを入れるとより安心です。
まとめ
今回はChatGPTを企業で導入するうえでの社内ルールの作り方とその利用例についてお伝えしました。
まだまだ新しい技術であり、今後も動きが多いと予想されますが、難しいからと放置しているといつのまにか、使っている企業や個人とは大きく差がついてしまうかもしれません。ぜひ今のうちに手間取りながらでも挑戦してみませんか?